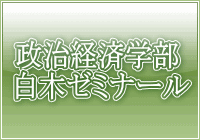政治経済学部白木ゼミナールのHPへようこそ。
What's Shiraki seminar like?
○研究内容
国際人的資源管理(Human Resouuce Management)をベースに、日本企業のアジアでの現地化や教育制度について、主に企業の労務管理の比較研究を行っています。内容としては、人事評価、教育制度、労働環境などを企業訪問等を通して比較、研究するほか、国際人的資源管理ということで、日本人海外派遣者の労務管理やグローバル企業における外国人の活用等も勉強しています。他に、付随するものとして、労働問題や労働政策など、労働の分野全般を必要に応じ学んでいます。
3年次は話し合って決定した教科書に基づいてプレゼンテーションを行います。その際、教科書の内容を掘り下げた内容をトピックとしてプレゼンを行います。特に新しい内容を扱うので、白熱した議論が行われます。流れはプレゼンに対してコメンテーターが質問をし、後は自由に質疑応答といった感じです。これを毎回二組を目安に行っています。実際に企業訪問や海外合宿を通して生の現場の話を聞くことで、知識・関心を深めていきます。4年次からは卒業論文にとりかかることになります。
○特徴1 海外合宿
7月最後〜8月前半に国内合宿が行われ、そこでは海外合宿に向けての勉強会などが開かれます。またレクを行いゼミ生・先生と交流を深めます。9月には海外合宿を行います。マレーシア、シンガポール、韓国、中国と毎年白木先生と話し合って決定します。行き先以外は主にゼミ生主体で決定します。現地では、現地の企業を訪問し、海外での派遣者や現地の社員の生の話を伺います。海外との大学との交流なども行います。
○特徴2 企業訪問
特定のテーマに基づいて企業訪問を行います。様々な企業の方から、教科書だけでは得ることのできない、全く異なった情報を得ることができます。毎年ゼミ生でテーマを設定し、足で情報を稼ぐ良い機会となっています。それをもとにして論文をまとめることになっています。
○特徴3 ディベート
毎年多くのゼミと定期的にディベートを行っています。早稲田内に留まらず、他大のゼミともディベートを通して交流する。ディベートを行うことで論理的な思考や、扱った分野の知識を深めることができます。
○サブゼミ
各自必要に応じて行っています。ディベートの準備や、企業訪問の準備などにも充てられます。ゼミ外ではOB・OGによる就職に関してのサブゼミを行っています。
○卒業論文
一例をあげると
「他民族国家マレーシアにおけるビジネスマインドの研究」
「日本企業における採用活動のあり方の効率性」
「人事評価制度の情報公開とモチベーション上昇との関連性」
「インドの女性労働と経済発展について」
「成果主義人事制度の導入について成果重視の評価制度に伴う人事制度は各企業に同じ傾向にある」
など、ゼミの研究テーマとは離れて、各自が設定したテーマを自分で調べて書くことになっていて、毎年各自テーマはばらばらです。
○進路先
外資系金融、商社、マスコミ、出版、銀行、各種メーカー、ベンチャー企業、コンサルなど、他業種に渡ってOBOGが活躍されています。
Who's Prof. M.Shiraki?
|
■白木三秀(しらきみつひで) 研究室:8号館503号室 ■専門分野 |
|
|
■著書論文 ■担当科目 ■所属学会 ■現在の研究課題 |
|